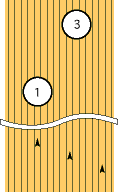
| まず、左の図を見て下さい。 これは、「ピン」・「スパット(三角印)」・「板目」の関係を示していて、1番・3番ピンを例にしています。 ファウルラインの少し先に、7個のスパット(三角印)があるのはみなさん御存知ですよね? このスパットは、板目にして5枚間隔で並んでいて、ピンは板目にして6枚間隔で並んでいることが左の図からわかってもらえると思います。 |
| 次に、右の図を見て下さい。 図の矢印は、板目に対してボ−ルが平行 の場合と、板目に対してボ−ルが斜め の場合とで、1番ピンの同じところにボ−ルが当たった後の ボ−ルの進行方向の例を示しています。 1本でも多くのピンを倒すには、合計10本のピンで構成された三角形の内側にボ−ルを食い込ませてあげるのが1番の近道です。このことを考えながら右の図を見ると、ボ−ルが板目に対して平行だとポケットに向かって一直線に進んでいるからストライクだ!と思っても、実際はボ−ルが食い込まずに外に跳ね返ってしまっています。 ところが、ボ−ルが板目に対して斜めに入射すると、外に跳ね返されずに三角形の内側に食い込んでいますね。 | 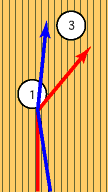
|
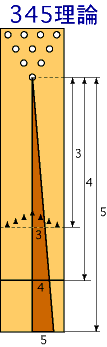
| 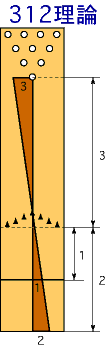
|
345 理論: これは、主にタップする時に参考にして欲しい考え方です。 構える立ち位置を移動してボ−ルを同じピンに行かせるには、どのスパットを狙えばよいかを説明したものです。 312 理論: これは、主にスペアを取る時に参考にして欲しい考え方です。 狙いどころのスパットを固定して 構える立ち位置を移動すると、ボ−ルがどのピンに行くかを説明したものです。 |