
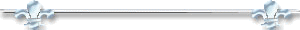

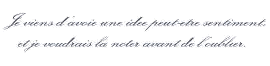
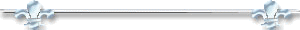
2005年01月09日
この前の記事で、カノン・フーガグループに関しては、それ以前の群に比し曲順にこだわる必要性もないのではないか、と記し、実際曲想からも音楽的,思考-発想の性質からも、確かにそう云えるとも思うのだが、ただ実際にバッハがひとつの曲集として実際この「フーガの技法」を――もし未完Fをも仕上げる所まで彼が生きられた場合に、であるが――彼自身の手で最終的に「仕上げる」際には、曲順に関してやはり一応は、こだわらざるを得なくなっただろうなと推測する時、Cp11の終了から、未完Fのはざまにこの群を置くのに、実際どのようにしたら最も自然に――と私は考える――組み立てることが出来るであろうか。
これはなかなか興味深いことである。
自然に聞こえる、ということは、諸作品自身と作品(諸々の主題)間の関係に於る様々な要素と側面を統合し、よりよい選択をする、ということであろうが、その結果ごく「耳触りのよい」仕上がり、になるという事は、じつはその背後の様々な要因を巧く処理しているということでもあるに違いない。
あの曲の次にこの曲が現れることの自然さ、それは、たとえ曲群が区切れまた次群に移行する際にであっても、かなりの程度要求されはしないだろうか。
そう考える時、私としては――少なくとも今の段階ではどうしても――レ(=D,主音)が主役として長く響く(殊に低音部にて印象的)Cp11のA4・§・⊃の絡みが織りなすあの劇的な収斂作用の後、すぐさま主題∀5の「ラ(A音)」が来る、というのは――つまりBWV15番(グレーザーによれば12番目=Canon
alla
Ottavia)が来る、というのは、――何か毎度ディスクが切り替わる度、若干の違和感を感じてしまう。
では、何が来ればしっくりするというのか...
私にとっては、やはり主題A8の登場がすんなりと受け容れやすい。
つまりBWV14番(グレーザーで15番目;Canon
per Augmentation in contrario
motu)である…。
何故ならA8は、Cp11の§や⊃とのそのまま遁走も可能な程に同じ動機が通底し、同時にみづからが主題の出だしから半音階進行色が濃厚(開始ではミの♭脱着が頻繁)で、この後延々と続く旋律が連動的にA-B-H-C間の動き、殊にシの♭脱着(B⇔Hの行き来)が頻繁となる性質である=未完F-第3主題の前哨。
実際高音部のVn,低音部のCv、これら掛け合う諸旋律、ともになめらかにBとHを行き交う。
と同時にこのA8自身、A4と∀4――Cp11にはA4主題そのものばかりでなく、転回形、∀4も登場する(第76〜80小節)ために、このBWV14のスタイル自身*にも似つかわしい。
*第5小節目〜のvc(チェロパート,A8の転回形兼時価2倍)の動きは、∀4(∀3の、といってもよいが)のvariationである
ということで、非常によく繋がるのである。
だがもしそれゆえに、カノングループの先頭がBWV14(主題A8)より始まる、となるとすると、この曲の終了仕方の後、耳にしっくりくるものはA6(BWV17;グレーザーで13番目)であり、次には∀7(BWV16;グレーザーで14番目,フルート&ヴィオラ)が待ち遠しい。
ここでこれらの楽器のすべらかな音色による頻繁な半音階脱着+音の跳躍で過ごす3つや6つに連なる8分と16分の連音符を聞き慣れた後、∀5(グレーザーがカノンの最初=12番目とするBWV15)の「16分音符×3」の連音符進行を聞く、ということになる訳**である。。。
そして鏡状フーガのBWV13;グレーザーで16番目のA9・∀9に移行、ということになる。
これも、案外しっくりくるパターンではないだろうか。
**…ただ本当はこのフルートのカデンツァで、またA8に戻りたくなる感覚もあるが...グレーザーやフスマンは、事実そうしている。
否ほんとうは∀5を飛ばして∀7の最後(フルートのカデンツァ)からそのまま鏡状フーガA9・∀9へと移行したい程である。
つまりそうすると∀5の存在位置がなくなってしまうということになる...
Cp11の後、A8を耳に出来ず、∀5(開始はラ=A音)をいきなり耳にする違和感と、∀7のカデンツァ後、(∀8へ至れず)∀5へと渡る違和感と、どちらがより大きいであろうか。
2005年01月10日
>Cp11の後、A8を耳に出来ず、
>∀5(開始はラ=A音)
>をいきなり耳にする違和感と、
>∀7のカデンツァ後、
>(∀8へ至れず)∀5へと渡る違和感と
>どちらがより大きいであろうか
であるならばいっその事、
A8(BWV14;グレーザー15番目)→A6(BWV17;グ13番目)→の後、
∀7(BWV16;グ14番目)へ行かずに先に∀5(BWV15;グレーザーがカノンの最初=12番目とするもの)に行ってしまい、(カノングループの)最後に∀7へ移行する方が自然である。(曲の終わり方、次曲の始まり方を考えても。)
そしてどのみち∀7→A8へと移行する自然な道が(私の考う方法を採る場合)すでに閉ざされてしまっているなら、∀5→∀7という順を巡り、∀7のなめらかなシンコペーションからそのまま鏡状Fグループの最初(∀9・A9)へと移行してしまうほうがはるかに自然で耳障りもよい。
とまれ、ここでこの問題を云々していても仕方がない。
次回からグレーザーの曲順にしたがい、BWV15(∀5)から分析に入る。
2005年01月11日
もうひとつ、グレーザーとフスマンとでは意見の異なった場所、つまりカノングループと鏡状フーガグループの順序の問題に就てだけ触れたい。
フスマンは、鏡状Fグループを、カノングループより先に置くのである。
中の曲順に関しては、二人の意見は変わらない。
これをどう考えたらよいか。
つまり未完Fの到来を直前に、カノンGの最後BWV14(G15;A8)を置くか――フスマン、鏡状Fの最後BWV12(a4;A1・∀1)を置くかということである。
どちらの最終曲も、ともに未完Fの前哨線的意味合いをおそらく他曲以上に多分に含む曲だといえる。
結論を云ってしまえば、私の感覚だとおそらくグレーザーのするように、カノングループを先に置き、鏡状FのBWV12で締めくくる――未完Fに渡される――、とするほうが(BWVの終わり方を噛みしめて思う時...)より強力であり荘厳だろうと思われる。
勿論、二人がともにカノングループの終わりに配置しているA8主題のBWV14も、カノン群の中で最も主題A系列の展開とともに未完F-第3主題の準備も着々な半音階脱着性の最も頻繁なスタイル――私自身にとっても、未完Fに近いCp11(§・⊃)の要素にグループの中で最も重なると思われる――となっており、カノンの中で最も意味深長で神妙な音楽であることはたしかであるが、鏡状Fの最終曲(曲順に関して私も全く同意したい)と比した場合、やはり後者を採りたい。
厳粛なコラール風の、この鏡状F-BWV12(A1・∀1)には、暗に全ての未完F主題への前兆――(控えめではあるが)B⇔Hの交換はもとより、第1,第2、そして勿論来たるべき第4(A1)主題――が、存るのである。
2005年01月12日
カノングループ
BVW15;グレーザー12番;主題∀5を巡って
Canon alla
Ottavia
それにしてもバッハが「フーガの技法」を貫く調性を、このポジシオン(ニ短調)に据えたこと自体、如何にBとHの交換作用を曲想の前提に置いていたかを物語る。
この点に於てみても、未完F第3主題を発想の前提にバッハがこのフーガを書いたということ、その意図を、真っ向から否定するレオンハルト等の人々の意見が、私には理解し難い。ニ短調とは、そもそもBとHの交換を音楽上余儀なくされ、或いは円滑自在に進めるための調性である。
このグループの存在は今以て謎であるとされる、カノン群。たしかに精神によってというばかりでなく多分に機知に富んだ発想からも、創作されている感はある。しかしそう云われるこのグループの筆頭とされる当BWV15でさえ、多分にB⇔Hをめぐる半音脱着、BからHへ、HからBへの精妙な交換作用が意図され、未完Fのうち最も象徴的なかの第3主題への準備がそこはかとなく施されている。
B-Hを巡る半音階の脱着は、以下の通りである。
第1声部の動きを主眼にして記すと、
まず第1〜8小節前半まではB支配であるが、8小節のH音から9小節まではH支配へ交換される。10小節〜11小節にはBへ戻る。
15〜18前半ではまたHが浮上したと思うと、18後半〜24にはすぐさまBが主役に躍り出る。25から再び30の最後尾にBが出現するまでは、またHが主役となっている。30最後尾のB音から39小節のHまでは、交代劇である。39からはしばらくの間明るいH支配が続く(〜62前半迄。)
62小節の中間にBが出現してからは、73までその支配となる。74の後尾にHが出現するが、まだBを主体とする旋律が80迄つづく。
Finale、とされるパッセージ(81〜最後迄)では、ほぼ2〜4小節毎に交代劇となり、最後はBの支配で終わる。
最終盤、殊に101〜102小節。この終わり間近の旋律はBしか登場しないが、その半音階メサージュは多分に未完F――第1主題(レラソファソラレ)の変容とともに――第3主題の半音階進行特有の精妙さを、意識させる。
♭シ
♭ミレ
♯ドレミラ
またこの曲には、これ以外の未完Fに於る他の主題の予兆も、感じられる。
主題∀5は、ジーグ風リズムではあるが∀1が基いとなっている。(若しくは∀3と言ってもよいだろう。)
他曲と同様当然つねにA1が基底に流れているといえるが、この曲独自にはその遁走を通しての変奏スタイル、例えば第5〜6小節の第1声部のパッセージなどは(このスタイルは、全く同旋律を4小節遅れで追う第2声部のそれを含め、何度か繰り返される。9〜10小節,変形パターンとして20〜22,29〜31小節等々)
或る種未完F第1主題の変形ともとれる。
(※視点を変えると、当パッセージ・未完F第1主題ともに、∀1(∀3,+A1・A3)の変奏であると云えるだろう。)
そしてまた、この曲の全体、すなわちカノン形式を用いたここでのA1主題の展開仕様そのものが、未完F第2主題を目指している(リズムこそは9/16だが、音列そのものに見い出せる意図として。)
2005年01月13日
カノンBWV17 グレーザー13番
Canon alla Duodecima in Contrapuncto alla
Quinta
未完F第3主題というのは、特有の雰囲気を持っている。
通常主題、とされる最初の3〜4小節部分のみの中にも集約的に充分示される通り、B支配(古旋律のような、レミファソラ
♭シドレ)のtoneから、近代の短調旋律であるH支配(レミファソラシ
♯ドレ)へとまさに上昇しようとする現場のような主題である。その部分ばかりでなしに、未完Fの中で繰られる主題の流れ、あの<全容>を考えても、旋律の動きはたえずHへの上昇と加えて更なる上昇(ホ短調への転調示唆)と逡巡、暗い逆戻り、また繰り返される上昇志向と後退、というように非常に悶々とした、かつ激烈な仕様である。
B-H運動に関わっているのは、何も第3主題のみではない。冒頭から出現する第1主題も、第2主題も、そもそも未完F全体で鳴らされる旋律の全てが、ニ短調という場、この位相にしてこそ可能な妙を駆使しながら、それぞれに壮絶なtoneでこの精巧なB-H劇を物語っていくといっても過言でない。だから第3主題が登場する迄には、その<精妙なる可塑性>への凄絶なる準備が、すでに十二分に整っている、といった風である。
さてカノンであるが、動きの細密な6連音符には始まる、二重対位法によるこの12度カノンは、例えば未完Fの全体的な印象としての精神性などと較べれば、やはりバッハらしく暗く知的であるが、凄絶さというよりは寧ろ見透かすような機知に富んでおり、透徹して視界が明るい。
だがここにて8小節差で織られていく双つの見事な旋律には、やはり巧妙なBからH、HからBへと繰り返される問答の糸が、やはり貫通している。
未完Fより暗鬱とした感がないのは、短調〜別の短調への転調の合間をつなぐ、長調(めいたもの)の介在時間が長いからということもあろう。
これは未完F(殊に第3主題に典型的)にもある現象だが、音楽的には古調めいたニ短調(レミファソラ
♭シドレ)から近代的なニ短調(レミファソラシ
#ドレ)に移調するには、その前提または間に長調(めいたtone)を介在させなければならない。
未完F第3主題では、――頭の中で、その旋律に添う和音の移行を思い描けば分かり易いが――あのB-A-C-H…
♭シ-ラ-ド-(natural)シ-#ド-レ-#ド-シ-#ド-#レ-ミ-シ-ミ-レ-ド#ド-レ...:第193〜201小節)という一連の短調旋律を分析すると、
まずB支配の古調めいたニ短調旋律(♭シ-ラ-ド;この時([ハ長調前提]→ヘ長調の和音が添う)⇒次にH支配の近代的短調旋律(シ-#ド-レ;ト長調→ニ短調添)⇒#ドシ
#ド
(イ長調添)⇒#レ_ミシミレ(ホ長調添)⇒ド(イ短調添)_⇒#ド(イ長調添)⇒レ(ニ短調添)、この後紆余曲折して束の間ハ長調に安んじ、すぐにまた同旋律を繰り返す、というふうに、暗にめまぐるしい長調乃至短調に添われた転調を内包している。
もっと単純化して言えば、(前提:ハ長調)-へ長調-ト長調-ニ短調-イ長調-ホ長調-イ短調-イ長調-ニ短調...(ハ長調)、という具合である。
これと似た兆候が、――もっと長調の占める息は長いが――このカノンBWV17にも見られるのである。
最も頻繁な転調(めいたもの)を示すのは第25〜34小節辺りで、ハ長調-(イ短調)-ニ短調-(イ長調)-ハ長調-古調ニ短調-(イ短調)-近代ニ短調、という形である。これは未完Fを殊に彷彿させる。
これ以外にも、B⇔H間の交代が、様々な転調を喚起している。B→Hの交代がニ短調からイ短調への転調のきっかけを与えたり(5小節)、H自身がイ短調からイ長調への移行を内包したり(18小節)、HからBの交代がイ長調からヘ長調への移行を呼び覚ましたり(19小節)再び今度はBからHへの交代でヘ長調からハ長調へと転調(23〜24小節)している(この後イ短調へ)。
このカノンの主題は基本主題A1を装飾し変形した形になっているが、Cp10-E主題などとの併走も可能な主題のように思える。また直接の併走は出来ないが、未完F第2主題(途中までは併走可能である)を生み出すか、変容させつつ生み出す可能性を抱いていると思われる。未完F第2主題をそれぞれに想起させる要素があるのは、他のカノン群の曲たちもおそらく同様である。
2005年01月14日
カノンBWV16 グレーザー14番
Canon alla Decima in Contorapuncto alla
Terza
基本主題の転回形∀1のシンコペーションである主題∀7。
細かく複雑な書き方をすることも出来るだろうが困難なので、この曲の特徴をごく単純化した表現で記すと、ニ短調という調性の曲とはいえ、内実としては主にへ長調系(へ長調志向,若しくは内在・前提の)古-ニ短調とハ長調系(ハ長調志向,若しくは内在・前提の)近代-ニ短調)と、また時にはイ長調系(イ長調志向,内在の)近代-ニ短調の交代劇、ということになる。主に、である。
もう少し細かく言えば、ホ長調やハ短調、ニ短調(ニ長調?)、イ短調、変ロ長調、変二長調などのニュアンスも含まれる部分があると云えるかも知れない。が大ざっぱに言って全体的色調として明る目のこのカノンは、そのニ短調という位相の中で実はへ長調・ハ長調、時にはイ長調とも言うべきtoneを伏在させつつその志向性を巧妙に交代し、展開していく楽章だと云える。
それは勿論のことながら、めくるめくB⇔Hの交代劇が及ぼす作用としてそうなるのであって、その因果関係からBを含む調(ヘ長調)とHを含む調(ハ長調・イ長調)が暗示的に背後にうごめくのである。
中でも興味深いのは、B支配とH支配が同一小節の中に見事に混在している、例えば第20〜21小節などの場所である。
高音部(ソプラノ)はその少し前からずっとB支配のtoneを保ちつづけているが(=ヘ長調志向的二短調)、低音部(バス)はこの時――20小節後半〜――H支配に変わり(=イ長調志向的ニ短調)、得も言われぬ巧妙な遁走を成立させている。この小節はBとHの支配両義性を帯びることにより古調と近代調の二重性を帯びている。31〜32小節など同様。
尚、第40小節から、ソプラノとバスの役割は交換され、冒頭からここまで10度のカノンを保っていたものが、以後は二重対位法により7度カノン(octv-C)へと転じている。
当カノンも他と同様、全容としてそうであろうが、殊に7小節後尾〜8小節のバスの動き、11小節後尾〜12小節のソプラノの動き(これらの転回形が15〜16,19〜20にあるが)、28〜32小節ソプラノの運動線などは、(octv飛びで幾らか極端化したうごきであるが)未完F第2主題の一種の前哨であると思われる。
勿論全体としてはひとつの旋律乃至小節内でのBとHの共存乃至両義性を確立することに主眼があり、未完F第3主題の存在を前提にしていると思われる。
|
|
|
|
|
|
|
|
|